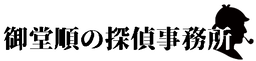バイバイ
物心ついた頃には、母親が側にいなかったように思う。父親はいつも、どこで何をしているのか不在が多く、たまに帰ってきても無口な男だった。
やがて少年は家を出て、一人で彷徨ううちに、新宿へと辿り着いた。
「おい、ガキ。ドアん前に座ってたら、俺が出入りできねェじゃねーかよ。どけ」
頭上から降りかかる無情な声に、座り込んでいた少年が顔をあげる。
薄汚い子供だ。
ボッサボサの髪の毛は油でテカっていたし、ボロ雑巾みたいな布きれを身に纏っている。
しかも裸足だ。
爪の間には泥が挟まって、もう何日も洗っていないように見えた。
今時はホームレスの子供だって、もう少し、まともな格好をしていよう。
「どこのレスだ?悪いが、おめぐみ出来るようなモンは、うちにはねェのよ……余所にいきな」
どん、と背中を足で小突かれて、少年が前のめりに倒れる。
それでも一言も言葉を発さない少年に呆れて男が側にしゃがみ込んだ時、真後ろから女が歩み寄ってきて「あんた、何してんの?あら……何?その子」と眉を潜めた。
男の名は御堂順。
女は、彼の妻で御堂未央という。
少年が座り込んでいた建物の持ち主で、表看板には『御堂探偵事務所』と書かれていた。
「おぅ、なんかわかんねぇが、ここにずっと座ってやがったんだよ」
順が答えるのへは生返事で、未央は夫の肩越しに少年を覗き込む。
薄汚れた顔に、目だけが狼のように爛々としている。
「なんなの?迷子?」
妻の問いに、順が首を傾げる。
「って訳でもなさそうだが……どうする?一応、警察につれていくか」
「そうね。交番に届けておきましょ」
まるで荷物扱いだ。
事務所に入れてあげる気が、二人揃って微塵もない。
「おいボウズ、名前、なんてェんだ?」
順が尋ねると、少年はジィッと黒い瞳で彼を見上げたまま、ぽつりと呟いた。
「サイガ、コウイチ」
「さいがぁ?どういう字を書くんだ」
珍しい苗字に、順の声もついつい裏返る。
少年は、その辺に転がっていた石を手に取り、地面に書き殴った。
それによると、『妻賀』と書くらしい。
ますますもって、珍しい苗字である。
「ねぇボク、どうして此処に座っていたの?探偵に用があったの?」
今度は未央が問いかける。
しかし光一は、だんまりだ。
「依頼人ってわけでもなさそうだな……仕方ねぇ、ちょっと行ってくらぁ」
「早く帰ってきてね」
光一の手を取り、順が歩き出す。
その背を見送ってから、改めて未央は周囲の匂いを嗅いでみる。
「……くっさぁい」
パタパタと手で二、三度仰いでから、ようやく事務所の中へと引っ込んだ。
妻賀光一と名乗った少年は、はたして交番でも無口を守り通した。
いわゆる、黙秘である。
警官と相談した末に光一は施設に送られる事となり、やがて施設の人が迎えに来てくれた。
施設の車に無理矢理乗せられるかたちで光一は連れて行かれて、何事もなくエンド――
と、なるはずであったのだが。
数日後。御堂夫妻は、予期しなかった光景に巡り会う事となる。
またしても、あの浮浪者然とした妻賀光一少年が、我が事務所の前に座り込んでいたのだ。
「……ちょっと。どういうことなの?あんた、あの子は養護施設に入れられたって言ったじゃない」
そう未央に怒られても、順だって納得がいかない。
口を尖らせ、言い返した。
「言ったよ。ちゃんとお迎えが来て、こいつを連れていくのも見届けたよ」
その光一が、何故、ここに戻ってきたのか。
本人に尋ねると、たった一言「ここがいい」とだけ答えた。
「なぁ~にが、いいんだよ!いいか?ここは迷子預かりセンターじゃねぇ。探偵事務所だっ」
順が威嚇しても、光一に動じる気配はない。
堂とした少年に苛ついたか、未央も夫の援護にまわった。
「大体、なんで服がボロボロのままなの?施設で新しい、お洋服をもらわなかったの?」
眉間に刻まれた無数の皺が、彼女の不機嫌を物語っている。
「この服は、母ちゃんが作った服だから」
光一の呟きに、知らず順の声も大きくなる。
「母ちゃん?どこにいるんだ、おめぇの母ちゃんは。連絡先を教えろよ、電話してやっから!」
だが、少年の返事は実にシンプルで。
「死んだ」
天国にいるのでは、とても連絡がつきそうにない。
そうなると、この子は孤児?ますますもって冗談ではない。
もう一度、施設の人を呼ばなくては。
悩む順を見上げて、光一が言った。
これまでよりも、ずっとハッキリした声色で。
「ここに置いて欲しい。けして邪魔にならない。邪魔は、しない」
「おい、だから此処は迷子センターじゃねぇって」
「お願いします」
順が何かを言いかける側から、光一は深々と頭をさげた。
三つ指ついて土下座する。
今時の子供が土下座とは珍しい。
「お、おい……未央、どうする?」
困った順が妻に尋ねると、彼女は「知らないっ!」と、ふてくされた様子で部屋に入っていってしまった。
――結局。
真剣な眼差しの光一に負けるようにして、御堂順は彼を居候させる事にしたのだった。
妻賀光一が住み着くようになってから、見る見るうちに御堂夫妻の夫婦仲は悪化していった。
元々夫婦仲は良い方ではなかったのだが、光一が来てからだ。
昼間でも、大声を張り上げて険悪な喧嘩をするようになったのは。
大体、光一を預かるのだって未央は納得していなかったのに、順が勝手に取り決めた。
そこんところも、未央の癇癪を刺激するには充分で。
日に日に光一へつらく当たる妻に辟易した順が嫌味を放ち、それに未央が逆ギレする。
茶碗や雑誌が空を飛ぶ事だって、日常茶飯事だ。
だんだん未央は家を留守にする事が多くなり、夫婦仲は破滅寸前までのカウントダウン。
「未央、今日も遅いね」
その日も光一が時計を見つめて呟くのへ、順が生返事する。
「あー。そうだな」
時計の針は夜の七時を指している。
まっとうな専業主婦なら、家にいなければおかしい時間だ。
「どら、仕方ねぇ。今日も俺が飯を作ってやる」
未央が家を空けるようになってから、夕食の支度は順の仕事になっていた。
家事などやったこともなかったが、最近では光一も「おいしい」と言えるほどの腕前になったと思う。
もっとも未央が作っていた頃、光一が料理を褒める事は一切なかった。
順が作るようになってからだ。
料理についての感想を述べるようになったのは。
未央が戻ってこなくて、案外、この少年は喜んでいるのやもしれない。
順としては、嫁には一刻も早く戻って来て欲しかったのだが……
今日の夕飯は肉じゃがと御飯。
付け合わせに、スルメの味噌漬けも作ってみた。
一口食べて、光一が「おいしい」と、ニッコリ微笑む。
「そうか、なら全部食べてもいいぞ」
投げやりに順は頷き、TVをつける。
時刻は七時半。未央が戻ってくる気配は微塵もない。
あのアマァ、今夜も友達の家にお泊まりか。
或いは、外に男でも作ったか?
最近の未央は何処で何をしているのか外泊が多い。
数日間、戻ってこないなどザラである。
考えてみれば、妻が誰とつきあっていて、どんな人と交流を持っていたかなど、順は何一つ知らない。
それでも夫婦面をしていたんだから、おかしな話だ。
未央とは恋愛結婚。ずっとそう思いこんできたが、光一のおかげで目が覚めた。
いや、目が覚めたというのは正しくない。
正しくは、夫婦の在り方を考え直させられた。
未央が帰ってきたら二人で話し合おう。
これからの事や、二人の関係について。
だが夫婦の話し合いの場は一度も和解の目を見ないまま、未央からの一方的な離婚通知を叩きつけられ、夫婦は正式に離婚した。
「ごめん」
何日目かの夕飯後、不意に光一が謝ってきた。
「あ~?何がだ」
振り仰ぐと、少年は泣きそうな顔で順を見つめていた。
「俺のせいで。未央、出て行っちゃったね」
「あぁ?勘違いすんな。元々、こうなる運命だったんだよ」
夫婦の離婚を気遣うとは、押しかけて居候した子供らしくもない。
「元々、俺達ァ仲良しこよしでもなかったんだ。だから、おめぇが心配するこっちゃねーぞ」
「でも」と、まだ何か言いたげな光一を遮ると、順は大きく窓を開けた。
空には煌々と月が輝いている。美しい満月だ。
「それより、お前には、これから色々と手伝ってもらうからな。掃除、洗濯、買い物、料理……未央がいねぇ分を含めた全部だ。大変だぞ?」
振り返って光一に笑いかけようとして、その顔がポカーンと呆ける。
「……あん?なんだよ、人が話しているってのに、どこ行きやがった。トイレか?」
光一が、いなくなっていたのだ。ぐるっと見渡しても、部屋の何処にもいない。
不意に足下へ擦り寄る生暖かさに、順は文字通り飛び上がる。
「うひゃあ!?」
慌てて下へ目をやると、そこにいたのは茶色の子犬。
なんだ?この野良犬、いつの間に部屋の中へ入ってきたんだ。
いや、ドアの開く音はしなかった。じゃあ、窓から?
いやいや、そんなはずはない。
だって、ここは二階だ。空を飛ぶ犬なんて、聞いた事もない。
突如出現した犬に驚いていると、どこからか光一の声がするもんだから、順は二度驚いた。
「ずっといるよ。手伝い、何でもする」
「こ、光一?どこだ、どこにいるんだ。それに、この犬ァ、なんだ?」
声は足下から聞こえてくる。
順と、口を開閉する犬とで目があった。
まさか……まさか、とは思うが。
目を丸くする順の前で、犬がコクリと頷く。
「犬じゃないよ。俺は狼。狼一族の末裔なんだ」
「い…………犬ゥッ!!」
リアルで腰を抜かしたのは、初めてだ。
尻餅をついた順は、わさわさと両手で床をかいて犬から距離を取ると、泡くって怒鳴り散らす。
「しゃべ、しゃべ、しゃべったぁぁぁッッ!!」
「だから、犬じゃないってば」
犬が、ぷぅっとふくれたように順には感じた。
いや、犬だから頬を膨らませる芸当など出来ないのだが、言葉尻にスネた感情を見たような気がしたのだ。
「俺だよ。光一、妻賀光一。俺はね、満月で変身する狼男なんだ」
「な……なん、だっ、って?」
頭が、どうにかなりそうだ。
だが現実問題として犬、じゃなかった狼は人の言葉を話し、光一は姿が見えない。
信じがたいが、この狼が光一で間違いないらしい。
大きく息を吸い込み、何度か深呼吸する。
ややあって、ようやく落ち着きを取り戻した順は、改めて光一を見下ろした。
狼男。そう彼は名乗ったが、どう見ても足下に座り込むのは、ただの茶色い犬だ。
「ふむ……人語を話せる以外に、なんかできねぇのか?芸当」
「強くなるんだ。人の時より、ずっとね」
得意げに光一は答えると、すっくと立ち上がった。二本の後ろ足だけで。
二足歩行の犬。
カトゥーンアニメなんかでは、よく見るが、実際に目の当たりにしてみると結構不気味だ。
「そのうち見せるよ。順がピンチに陥った時には」
いつ、そのピンチが来るのかは判らないが、その時は助けてもらおうじゃないか。
そんなことより、と話を戻して順が言う。
「強さは今んとこ必要ねぇ。お前が覚えなきゃいけないことは、ごまんとあるんだ。まずは料理、そして掃除と洗濯だな。会計なんかも、そのうち覚えてもらうぞ?」
「うん」
コクリと素直に頷き、光一が後ろ足で胡座をかく。
「なんでもやるよ。ここに置いてくれた恩返しだからね」
今時の子供にしては、随分と古風な言いまわしだ。
「ほぉ~。できれば未央がいる時にもして欲しかったモンだがな、恩返しってやつを」
つい飛び出た順の嫌味に、やや影を落として光一が俯く。
「ごめん。俺、あの人はどうしても好きになれなくて……」
「どうして?」
そういや、この子は未央には最後まで懐かなかった。どうしてだろう?
性根の優しい女ではないものの、美人だしグラマーだし、彼女は基本的に明るい性格だ。
表面上だけで言うなれば、けして付き合いにくい奴ではなかったはず。
順の問いに顔をあげ、光一は囁くように答えた。
「あの人……銀のアクセサリーを、いつも身につけていた。怖かったんだ」
「ハァ?銀のアクセ?なぁ~んで、それが怖いんだよォ」
訳のわからない理由だ。
そんな理由で嫌われていたんじゃ、未央も到底納得できまい。
ま、だからこそ、出ていったんだとも言えるわけで。
結果的には光一が追い出したようなもんだが、引き留められなかった順にも責任はある。
何より、この程度で壊れるような夫婦仲に未練など、ない。
それよりも今は新しく出来た家族、息子ともいえる年齢の小さな子供について考えるだけで精一杯だ。
何故だか知らないが、彼も自分に懐いている。
ならば、せめて光一が成人するまでは、面倒を見てやろうと順は考えた。
未央との間に子供がいなかったのは、不幸中の幸いだった。
二人の子供を抱えるハメになっていたら、光一の面倒だって見られたかどうか。
「光一」
ポンと狼の頭に手を置くと、すぐに光一が返事する。
「なに?」
真っ直ぐな瞳が眩しくて、順は心なし視線を逸らしながらも、はっきりと伝えた。
「これからも、よろしくな。その、家族として」
家族。その言葉を、じっくり心へ染みこませるように、やや空白を置いてから。
「……うん!」
狼は元気よく頷いた。
おしまい